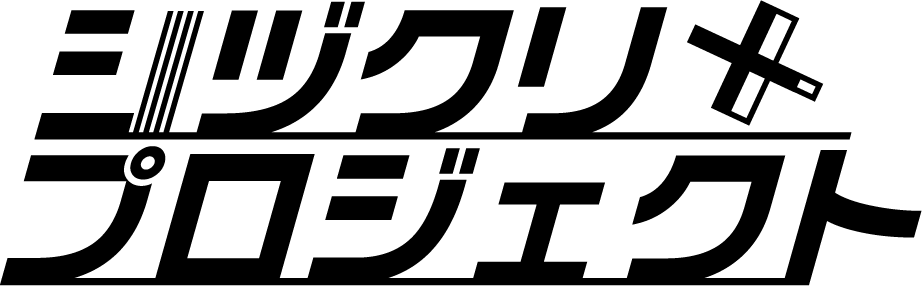
第2回シヅクリ研修レポート 〜企業人と教員が共に体験する探究学習の『旅』で見つけた気づきや学び〜
2025年8月5日から8日にかけて、静岡県内4会場(沼津・浜松・静岡)で「第2回シヅクリ研修会」を開催しました。
シヅクリPROJECTに参画する企業担当者と学校教職員が合同チームとなり、生徒と同じ探究学習のプロセスを追体験。
本研修会は、教員と企業の連携強化と、探究学習におけるファシリテーションについて体験的に理解していただくことを目的に実施しました。

研修会の目的とプログラム概要
研修は「生徒と同じ探究の旅を体験すること」を軸に、アイデア創出やファシリテーションの実践を通して参加者自身の関わり方や考え方を見つめ直す場として企画しました。
地域のリソースと企業リソースを活用したブレインストーミング、グループでの企画づくり、発表、そして振り返りを通じて、心理的安全性のある場づくりや多様性の価値を実感していただきました。
研修の後半には、参加企業ごとに分かれて企業紹介や特色を共有。教員が企業理解を深め、学校と企業の連携を促進する機会となりました。
参加者からの多様な気づき — 5つの視点で振り返る
研修後のリフレクションシートや対話で寄せられたコメントを分析すると、参加者は以下の5つの主要な気づきを得ていることが分かりました。
安心感と心理的安全性が創造性を促進する
「正直な意見を遠慮なく言える安心感が、アイデアの質を高める」「年齢や立場を越えて意見を自由に共有できる場づくりが鍵」といった声が多数。
多様なメンバーが対話を通じて意見を重ねることで、一人では想像もつかない新しい発想が生まれる体験を実感しました。
まさに「心理的安全性」は探究学習のみならず、組織のイノベーション促進に不可欠な要素であることを改めて認識しています。
「安心しているからこそ、正直恥ずかしく感じるような意見もポンポン発言することができた。さまざまな意見がどんどん出てくることで、アイデアの質が向上していったことを感じた。」
「アイデアを0から産む必要はない。心理的安全性のある雰囲気の中で、思いついたことを言ってみる、それに他のメンバーが便乗する。アイデアを上乗せすることで面白いアイデアに仕上がっていく、この過程が面白い。」

イラストやビジュアルによる「見える化」が共通理解を深める
言葉だけでは捉えきれない意識のズレを、イラストで表現し共有することで、理解の差異を発見・調整できたという声も。
これは教室や企業の会議での情報共有において、視覚的表現の重要性を示しています。
参加者からは「口頭の説明で納得していても認識がずれていることが多い」「イメージの違いを早期に修正できる」などのコメントが寄せられ、実践的な効果が実感されました。

「各自の考えを絵で表現してみる時間が大きな気づきになった。会話を進めていく中で、自分の中で当たり前だと思っていたことや、共通認識として伝わっているであろうことが、チームの仲間と全然違っていた。」
「言葉で見えなかったことが絵にすることによってそれぞれの考えが明確になった。そこには共通理解できていると思ったことが実は少しずつずれがあり、それが新たな発見になりました。」
多様な価値観の融合から生まれる新たな発想
異なる年代、職種、背景を持つメンバーと対話し協働することで、自分ひとりでは思いつかない発想や視点が得られたという感想が多くありました。
特に固定概念を取り払い、自由にアイデアを出し合うことで、心理的安全性の高い場が創られ、思考の幅が広がることを体験。
この多様性の活用は、学校現場での生徒の探究活動や企業のチームビルディングにおいても有効だという認識を持たれた方がたくさんいらっしゃいました。
「普段は設計という立場上、現実化できるかが大前提となるため、それを取り払ったときにこれだけ自由な発想が生まれるのかと驚いた。アイデア出しという視点であればとても有効だと思うので、業務にも取り入れてみたい。」
「自分が10人いても発想は広がらない。いろんな人がいるからアイデアが広がることを実感した。」
「固定概念に左右されない考えを持っていると思っていたが、自分の考えこそが固定概念であると感じた。広く多くの人の考えや意見に触れることで、アイデアがさらに広がることを学べた。」

「問いかけ」の力と「Yes, and思考」の重要性
参加者は、意見を否定せずに受け止め広げる「Yes, and思考」が話しやすい雰囲気をつくり、アイデア拡散に繋がることを学びました。
また、適切な問いかけによって、思考が深まり、まだ言葉になっていない気づきを掘り下げるプロセスの大切さを実感。
これらはファシリテーションのスキルとしても、教室や企業の議論の質を高める上で欠かせないと印象に残った方も少なくありませんでした。
「共有→拡散していくにあたって、メンバーの考えや思いが広がっていく瞬間が楽しかった。Noではなく、『Yes and思考』にすることで自然と考えが広がり、受け入れていく雰囲気ができて話しやすかった。」
「問いかけることがとても重要なプロセス。いま困っていてなぜ手が止まっているのか?問いかけで話が広がり、まだ言葉になっていない思いも掘り下げられる。」
「自分は違和感に注目しがちで、すぐにダメ出しをしてしまう。『Yes and思考』になるトレーニングが必要だと感じた。」

試行錯誤や「混沌」の中にある学び
結果だけでなく、その過程での議論や試行錯誤自体に価値があるという理解が深まりました。
また、「混沌」と感じる状況もプロセスの一部であり、そこであきらめず会話を続けることでブレイクスルーが起こる体験が共有されました。
この視点は、変化の激しい現代の教育・ビジネス環境において、非常に重要なマインドセットです。
「結果だけでなく、話し合いや試行錯誤のプロセスの中に学びや気づきがあると実感。チーム内で話し合うことで、考えや自分の意見に変化があった。」
「混沌の状況は悪い方向だと思っていたが、事前に知り取り組んだことで、混沌をポジティブに捉えられた。」
「探究のプロセスの中で混沌の時間が長かったが、メンバーとの雑談からキーワードが生まれ、話が進んだ。アイデアが詰まった時も会話を止めてはいけないと強く感じた。」

研修を経て生まれた今後への意欲と具体的なアクション
参加者は生徒や自身の業務に活かすため、以下のような具体的な取り組みや決意を述べています。
・生徒が「考える楽しさ」を感じられるよう、問いかけや対話の時間を積極的に設ける
・教室や会議で、心理的安全性の確保に注力し、否定しない雰囲気づくりを推進する
・異なる意見や価値観に積極的に耳を傾け、チームのアイデア創出を促進する
・話し合いの「混沌」や壁にぶつかる瞬間をチャンスと捉え、問いかけを用いて突破口を探る
・言葉だけでなく、図やイラストを使った「見える化」を教育現場や業務で取り入れる
こうした意識改革と具体的行動は、シヅクリが大切にしている『共に学び合い、共に未来を創る』というビジョンの実現に向けて、企業と学校が手を携えて進んでいくための大切な一歩です。

シヅクリの今後の展望
シヅクリは、企業人と教員が互いに学び合い、共に探究活動を深めることで、地域の未来を拓く人財育成とイノベーション創出を目指しています。
今回の研修会で得られた多様な気づきを共有し、より多くの学校と企業が連携していく体制づくりを進めてまいります。
参加者の皆様、そしてご協力いただいた企業・学校関係者の方々に心から感謝申し上げます。
今後もシヅクリPROJECTへのご支援・ご参加をよろしくお願いいたします。
企業の取り組み概要や、
気になることがございましたら
まずはお問い合わせしていただければ幸いです。









